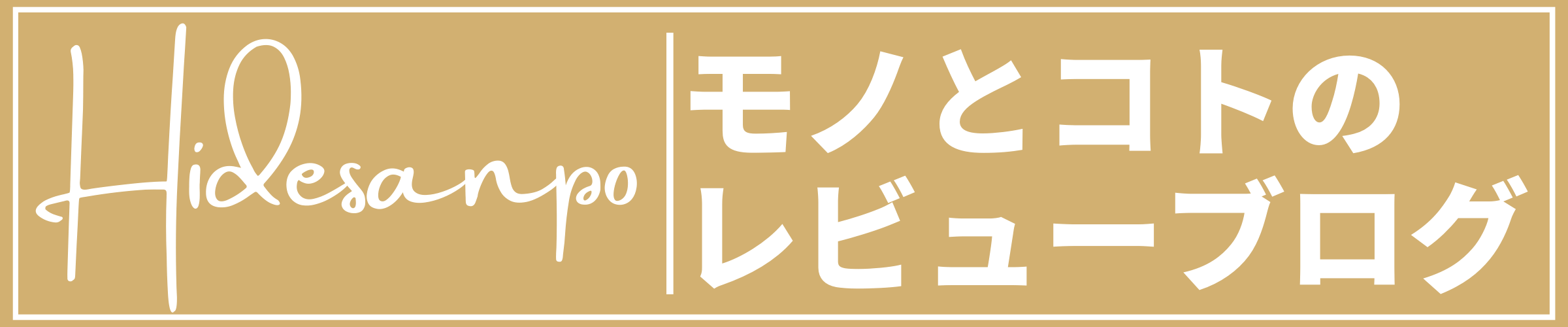この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
4輪のオートマ自動車の運転の際
信号待ちをしていて、N(ニュートラル)でサイドブレーキをかけて足を離す人がいます。
これってどういう意味があるのでしょうか?
また、危険ではないのでしょうか?
実は信号待ちをしていて、N(ニュートラル)でサイドブレーキをかけて足を離す行為は
燃費向上や足を休めるという考えから行っているようなのですが、
結論から言うと、この行為は大変危険です。
この記事では危険な理由と信号待ちをしていて、N(ニュートラル)でサイドブレーキをかけて足を離す意味について
くわしくお伝えしていきます。
オートマの信号待ちでN(ニュートラル)ならブレーキ踏まなくていいは危険

オートマ車の信号待ちの際にN(ニュートラル)レンジに入れておくと
足をブレーキから離せる場合がありますが、様々な危険やデメリットがあります。
急発進してしまう危険がある
N(ニュートラル)に入れていることを忘れて、アクセルペダルを踏んでしまい発進せず、
あわててDレンジに入れると一気に加速してしまうということがあります。
これ超危険です。
坂道であれば車体が動く危険がある
信号待ちの停車時にN(ニュートラル)にするクセがあっても
明らかな坂道であれば、自然とフットブレーキをかけると思いますが、
なだらかな坂でN(ニュートラル)にしてしまうと傾斜に気づかずに車体が動いてしまう可能性があります。
結果、追突し事故になるということもあるので、注意が必要です。
ブレーキランプが点灯せず、後続車に分かりにくい 追突の危険

信号待ちでN(ニュートラル)にしサイドブレーキをかけ、ブレーキを踏まないことを選択した場合に起こるのが、
車後方のブレーキランプの無点灯です。
後続車にブレーキをかけたことを知らせるブレーキランプは追突を防ぐための役割を担っています。
ですので、停車時にこのブレーキランプが点灯していないと一見走行しているように見えるため、
後続車は自車のことを停止していないと見誤る可能性もあります。
特に夕方から夜にかけての間、ライトを点灯するかどうか迷うような時間帯にブレーキランプが点灯していないと
ただでさえ前方が見にくい時間帯なので、危険度が増すといっていいでしょう。
むやみなニュートラルへの切り替えは故障の原因になる
走行中のクラッチの負荷よりも、停止している時の断続的な負荷や衝撃のほうが機械への負荷が高くなりますし、
頻繁にレンジの切り替えをおこなうとクラッチ板が減りやすくなり、トラブルの原因にもなります。
ただ、平成の後半に出た車種の場合はクラッチ関係の部品の耐久性も確保されているという話もありますので、
すぐにトラブルが起こるということはなさそうです。
オートマの信号待ちでN(ニュートラル)にする意味は?

燃費にいいと聞いたから
N(ニュートラル)にしておくと燃費がよくなると聞いたから。という人がいます。
確かにDレンジのままで停車するとトルクコンバーターに負荷がかかっているので燃費は悪くなります。
ですが、現在はDレンジであっても車がアイドリング中であると判断すれば、CVTのクラッチを切り、トルクコンバーターの負荷をなくす「ニュートラルアイドル制御」というシステムが導入されています。
このため、燃費悪化は最小限に食い止められているので、かならずしもN(ニュートラル)レンジにする必要はなくなりました。
また、最近の車ではアイドリングストップ機構を搭載したものが増えてきています。
アイドリングストップ機構を搭載した車の場合にニュートラルにシフトを入れるとアイドリングストップがキャンセルされてしまい、
結果的に燃費が悪くなります。
足を休めるため
足を休めるためにN(ニュートラル)レンジにシフトを入れ、サイドブレーキをかけてペダルから足を離すという方もいます。
ところが、危険なところで説明したように誤発信の可能性が出てくるのでおすすめしません。
足を休めるのであれば、P(パーキング)に入れて、サイドブレーキをかけたほうがいいです。
誤発信の可能性もなくなりますし。
ただし、P(パーキング)に入れて、サイドブレーキをかけたとしても
フットブレーキを踏んでいないので、後部のブレーキランプが点灯しません。(オートブレーキホールドではない場合)
かといって、ハザードをつけたりすると
故障かと思われて追い抜かれたり、思わぬ事故を誘発する危険もあるので、おすすめしません。
個人の意見としてはどうしてもの場合はニュートラルより、パーキング。
パーキングよりDレンジでのフットブレーキがいいでしょう。
タクシーの運転手さんがするところを見たことがあるから

タクシーに乗った際に運転手さんがオートマ車でニュートラルにするところを見たことがあるかもしれません。
この場合は車の仕様が影響しています。
タクシー専用車のクラウンセダンやクラウンコンフォート、コンフォートのオートマ(AT車)に標準装備されている
アイドリングストップ機構がNまたはPにシフトを入れると作動するためなのです。
運転のプロがするのだからという理由でマイカーでもやってみようと思われるかもしれませんが、
上記のような理由がありますので、うのみにしないように気を付けてください。
マニュアル車の名残りだから
ニュートラルに入れて、サイドブレーキを効かせておくことが当たり前でした。
この理由は万が一クラッチから足が滑るなどして離れた際に
フットブレーキを踏んでいたとしても、トルクが大きい1速だと車体が動いてしまい追突してしまうことを防ぐためでした。
ところがオートマ車の場合はクリープ現象はあるものの、
フットブレーキをしっかり踏んでいれば車は動くことはありませんし、
ニュートラルにしておくことで、急発進の可能性を高めるよりは
Dレンジでフットブレーキをしっかり踏んでおくことのメリットのほうが大きくなっています。
オートマ車のN(ニュートラル)っていつ使うの?
レッカー車による牽引(けんいん)の時だけに使うと覚えておきましょう。
ニュートラルになっていれば、エンジンをかけていなくても車を引っ張って動かすことができるからです。
その他、レアケースですがガソリン切れなどで車をその場を動かさざるをえなくなった時には、
運転席に一人乗り込み、ニュートラルにしておき、数人がかりで押して動かすという手段もあります。
サイドブレーキ(パーキングブレーキ)ってどういう役割があるの?

ところで、サイドブレーキ(足踏み式パーキングブレーキを含む)ってどういう役割があるのでしょうか?
ひとつの疑問として、ニュートラルにしてサイドブレーキをかけたとしても動き出す危険があるなら、
サイドブレーキって車の制動にはあまり役にたっていないような気もします。
またサイドブレーキを解除し忘れて走行してしまったという経験を持っている方も多いと思いますが、
要はサイドブレーキにはそれくらいの制動力しかありません。
ではサイドブレーキ(パーキングブレーキ)の役割ってなんなのでしょう?
その答えですが、サイドブレーキは停車時に使うブレーキなのです。
フットブレーキと合わせてどうして2つもブレーキが備わっているかというと、
フットブレーキは走行中のブレーキ。
サイドブレーキは停車中のブレーキ。
・・・という役割があります。
ちなみに、フットブレーキは油圧式のため、エンジンが動いていないとしっかり効きません。
エンジンが停止した状態で車が動いた場合、フットブレーキはペダルが通常の約5倍重くなるというデータもあります。
そのため、エンジンが停止している停車中はサイドブレーキ(パーキングブレーキ)で
車を動かないようにしておくということになります。(エンジンオフの停車中はパーキングシフトと合わせて使用してください。)
なお、パーキングレンジとサイドブレーキを併用する理由は、パーキングレンジの制動力が壊れた際に保険としてサイドブレーキをかけておくという意味もあります。
ですので、サイドブレーキは重要な役割をになっていますので、
適切に使うようにしたほうがよいでしょう。
オートマ車の信号待ちでN(ニュートラル)を使わない 正しい停車の仕方

ここまで、オートマ車の信号待ちでN(ニュートラル)にする理由や危険性をお伝えしてきました。
最終的に現代のオートマ車においてどういう信号待ちの際の停車がいいのかをお伝えします。
Dレンジでブレーキペダルを踏んでおく が正解です。
▼Dレンジでブレーキペダルを踏んでおく理由は以下のとおり。
- 急発進しない
- ブレーキランプを点灯させられる
- アイドリングストップがはたらく
安全性と、最近の車に備わっているエコ機能を働かせたほうが燃費にいいためです。
もし、どうしても足が疲れた場合はPにして、サイドブレーキ。
というのが安全ですね。
ただ、ブレーキランプは点灯しないので、そのことは認識しておいた方がいいです。
また、近年では「オートブレーキホールド」と呼ばれる機能を備えた車種も出てきています。
この機能があれば、Dレンジに入っていても完全に停車すればブレーキペダルを離したとしても停車してくれますので、
足が疲れなくてすみます。
発進の際は、アクセルを踏むだけで「オートブレーキホールド」が解除されスムーズに車を走らせることができます。
安全性も快適性も重視するというなら「オートブレーキホールド」のついた車種に買い替えるというのもアリだと思います。
オートマ車の信号待ちでN(ニュートラル)でブレーキ踏まないのは危険 まとめ
今回の記事ではオートマ車の信号待ちでN(ニュートラル)でブレーキ踏まないのは危険な理由をお伝えしました。
最近の車では以前のものより仕組みが変わってきているものも多くなっています。
車を乗り換える際などに一度今までの常識を見直してみるのも必要な時代になっているのかもしれませんね。
それでは、また。